科学者にも哲学者にも解けなかった「意識の謎」とは何か?
赤いものを見ると、脳のニューロンに電気インパルスが流れ、「赤い」という感覚が生じます。
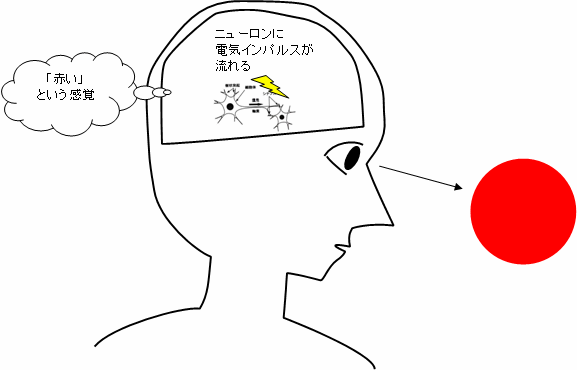
この、赤い色を見たときに脳内のニューロンに流れる「電気信号自体」は、「赤い」という「感覚そのもの」ではありません。
もちろん、(1)ニューロンの発火と(2)赤いという感覚の発生は、因果関係もしくはなんらかの対応関係がありますが、両者は別物です。
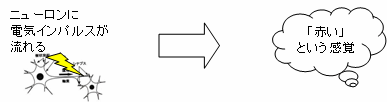
つまり、脳のニューロンの活動を、分子レベルでどんなに精密に観察しまくっても、「赤い」とか「冷たい」とかいう「感覚それ自体」は、どこにも見つからないのです。
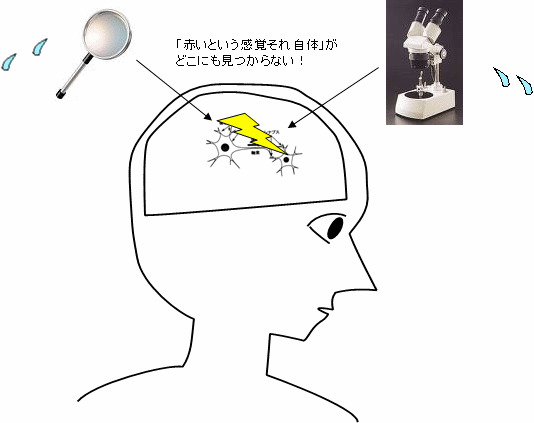
どんなに精密な機械で調べても、活発に電気インパルスを飛ばし合い、シナプスから神経伝達物質を放出しているニューラルネットワークが見えるだけです。*1
では、この「赤い」とか「冷たい」とかいう感覚が、ニューロンの分子と電子の活動パターンという物理化学的なもので説明不可能なものだとしたら、「赤い」とか「冷たい」という感覚は、「物理現象を超越した何か」なのでしょうか?
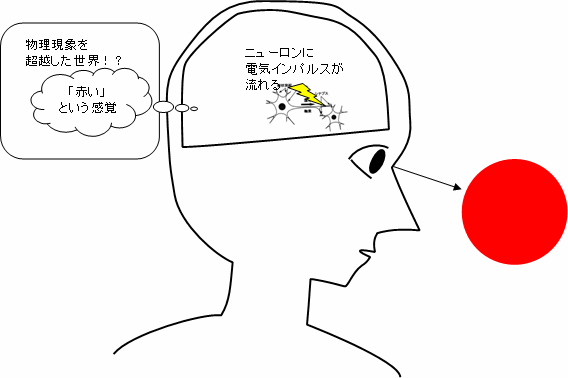
これは、感覚だけでなく、「意識」も同じ話です。
脳のニューロンの活動をいくら精密に調べても、「現にいま、こうして世界を眺め、感じている」自分の意識は、どこにも見つからないのです。
「脳の物理現象によって、意識を説明できない」ということは、「意識」とは、物理現象を超越した、霊や魂のようなものなのでしょうか?
核磁気共鳴画像法や陽電子断層撮影法などの、脳の測定機器がどんなに進歩しても、測定できるのは、あくまで、物理現象である、分子、原子、電子などの物理的な活動でしかなく、それとは別物である「意識」を測定することはできません。
そして、物理現象でないものは、科学では解明が不可能です。
なぜなら、科学が扱えるのは、物理現象だけだからです。
したがって、意識の謎は、科学によっては解明不可能なのです。
そして、もし、「感覚も意識のない人間」がいたとしても、我々はそれに気づくことは出来ません。
たとえば、次の図で、赤い色を見たときに、人間AもBも、同じようにニューロンは発火するのですが、人間Bでは、意識の中で「赤い」という感覚が生じるのに対し、人間Aでは単にニューロンが発火するだけで、「赤い」という感覚は生じません。そもそも、人間Aには、それを感じ取る「意識」がありません。
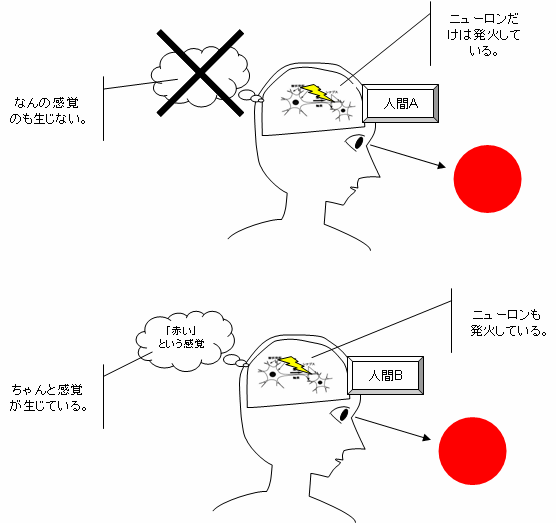
そのような二人の人間がいたとき、「感覚も意識のある人間」である人間Bの脳内のニューロンの活動は、「感覚や意識のない人間」人間Aの脳内のニューロンの活動と、まったく同じです。
脳は一種のコンピュータであり、外部からの刺激という入力データを受け取って、計算処理し、次の行動を起こすという出力をする装置です。この、タンパク質コンピュータとしての脳の働きは、意識のあるなしとは関係なく動きます。もちろん、アフォーダンス理論っぽく、脳だけでなく、とりまく環境全体がコンピュータだと考えても同じ話で、意識の存在の有無とは関係なく、環境を含めた全体が計算装置として動作します。
なので、意識のある人間も、ない人間も、外部からの刺激に応じて行動するだけで、外部から見ただけでは、その人間に意識があるか無いかは、原理的に判別不可能なのです。
このことから、たとえば、この、「現に世界が見えている感じ」があるのは、あなただけで、あなた以外の全ての人間が、感覚も意識もないタンパク質ロボットのような存在だったとしても、あなたはそれに気がつくことはできません。
女性が本当に子供を産む機械であるかどうかは、判別不可能なのです。
また、逆に、冷蔵庫やパソコンに感覚や意識があったとしても、あなたはそれに気がつくことはできません。
じつは、これらの感覚や意識の問題は、クオリアや哲学的ゾンビなどのキーワードで、哲学者たちのあいだで、長年にわたってさんざん議論されてきたにも関わらず、いまだに結論の出ていない難問です。
意識の謎を解く
たとえば、ここに花子さんという人間がいたとします。
花子さんの意識の在り方の構造は、原理的に、必ず次の①と②のどちらかになります。
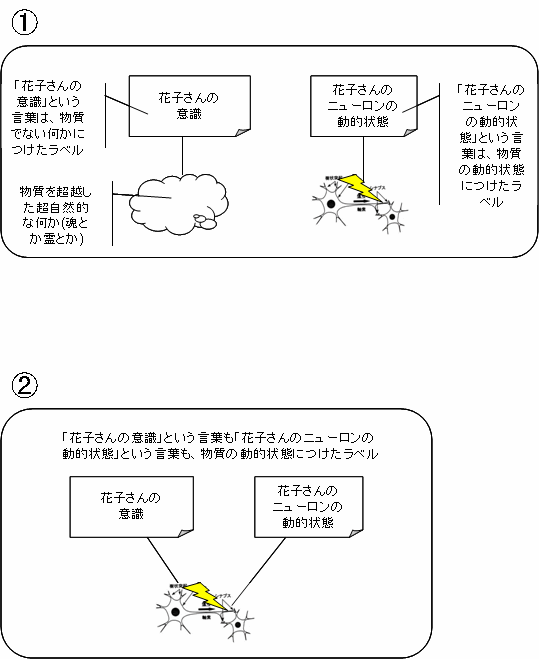
このうち、①は、「花子さんのニューロンの動的状態」とは別に、「花子さんの意識」という「物理現象ではない何か」が存在するという世界構造です。
この場合、「花子さんの意識」という言葉は、「物理現象を超越した何か」に貼られたラベルになります。
また、「花子さんのニューロンの動的状態」という言葉は、ニューロンが連鎖的に発火し、神経伝達物質が放出されている状態そのものに貼られたラベルになります。
もし、世界の真の構造が①のようなものだとしたら、話は簡単です。
意識の謎など、どこにもありません。
意識は物理現象ではないのだから、科学だろうと、哲学だろうと、意識は原理的に、いかなる測定も不可能であり、存在の証明も反証も原理的に不可能です。
従って、意識の謎に挑み続ける偉大な科学者、茂木健一郎先生がいくら頑張っても、その努力が実ることは原理的にありえません。
また、②は、「この世界には物理現象を超越したものは一切存在しない。」という世界構造です。
物理現象以外のものが何も存在しない世界構造です。
その場合、「花子さんの意識」という言葉は、花子さんのニューロンの物理的状態そのものに貼られたラベルに過ぎません。なぜなら、物理状態以外のものが存在しないのだから、「何か」が存在するとしたら、それは物理状態以外のものではなく、ニューロンの動的物理状態とシンクロして動作する意識というものの実体があるなら、そのニューロンの動的状態そのもの以外にありえないからです。
そして、「花子さんのニューロンの動的状態」という言葉は、「花子さんの意識」という言葉がラベルとして貼られたものと同じものにラベルとして貼られています。
もし、世界の真の構造が②だとしたら、確かに「なぜ、いくらニューロンを解析しても、「赤いという感覚それ自体」が見あたらないのだろう?」という、本質的な謎が発生します。
科学者や哲学者が、このような謎に悩んでいるとき、その「科学者/哲学者自身の脳」の中は、次のような物理状態になっています。

まず、世界の構造は②の「この世界には物理現象を超越したものは一切存在しない」という前提ですから、あらゆる感覚も、思考も、純粋な物理状態として記述されています。
これは、パソコンの中のオブジェクトが映像だろうが音声だろうがプログラムだろうがデータだろうが関係なく、すべてがビット(01データ)で記述されているのと同じです。
そして、この謎について考えている科学者/哲学者自身の、すべての感覚と思考は、ニューロンの動的状態(発火したり、神経伝達物質が放出されたり)として記述されていると仮定します。
この場合、この謎に関係する脳内ニューロン塊の動的状態は、2カ所あると考えます。
2つのニューロンの塊が、それぞれ別の場所で、電気インパルスだのシナプス発火だのをしながら活動しているわけですね。
まず、この図の(A)「赤いという感覚それ自体」を記述しているニューロン塊の動的状態があります。
このニューロンは、実際に赤いものを目にしたときに発火するニューロンです。
「このニューロン塊は、赤いという感覚が生じたときに発火する」のではなく、
「このニューロンが発火することと、赤いという感覚が生ずることは、同一のこと」です。
そして、(B)は、『「赤いという感覚それ自体」を記述するニューロン塊の動的状態』を思い浮かべる思考を記述するニューロン塊の動的状態です。
この場合、(B)のニューロン塊の動的状態の部分で、いくら科学的な分析や思考を積み重ねることで(B)を発火させまくっても、それはあくまで【『「赤いという感覚それ自体」を記述するニューロン塊の動的状態』を思い浮かべる思考を記述するニューロン塊の動的状態】であって、(A)の『「赤いという感覚それ自体」を記述するニューロン塊の動的状態』と同じ状態にはなりえません。
(A)は「〜という感覚」という直接的な感覚経験の記述であるのに対し、(B)は「〜という物理現象」という科学の記述です。科学の言葉で「〜という感覚」を記述するには、それをいったん科学の言葉である「〜という物理現象」という記述に翻訳するしかありません。しかし、翻訳した時点で、それはもはや「〜という物理現象」であって、「〜という感覚」という直接的な感覚経験そのものではなくなってしまうのです。
要するに、次の図のように、思考のクラスが違うのです。
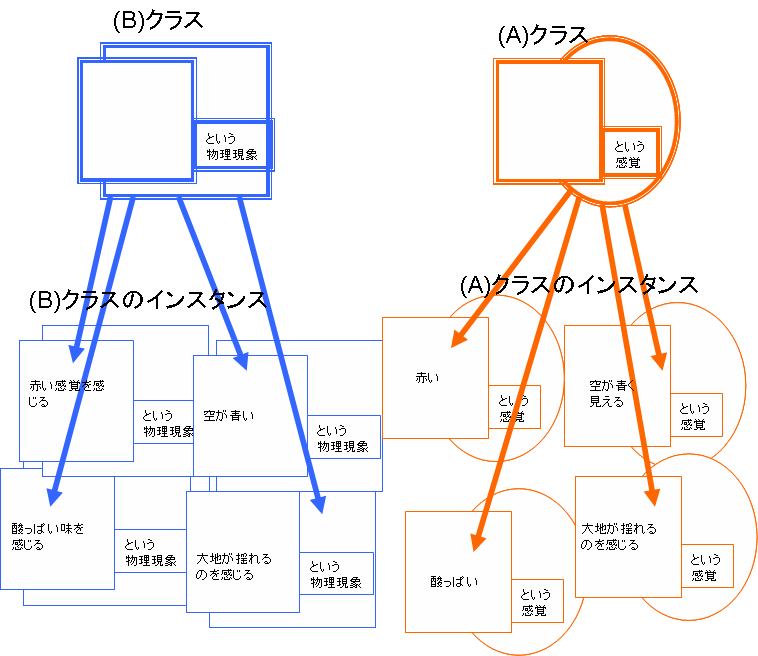
(B)クラスのインスタンスをいくら生成しても、それは必ず
「〜という物理現象」
という記述インスタンスになってしまうのです。
また、(A)クラスのインスタンスをいくら生成しても、
「〜という感覚」
という記述インスタンスになってしまうのです。
したがって、科学的な調査、分析、思考を無限に積み重ねて(B)クラスのインスタンスを膨大に生成し、組み立て、バベルの塔を築き上げても、絶対に(A)クラスのインスタンスにはなりえないのです。
意識についても同じです。「現に、世界が見えている感じ」というのは、(A)クラスに所属するものであって、それを記述しようとする思考は全て(B)クラスの思考になってしまうので、いくら意識とは何なのかの思索を積み重ねても、決して(A)クラスのインスタンスにはならないのです。原理的にならないのです。
つまり、意識の謎とは、(A)のクラスからたくさんインスタンスを生成すれば、いつかは必ず(B)クラスのインスタンスが生成されるはずだ、という前提が生み出した思考の錯覚なのです。
もちろん、前提を立てること自体は、何も問題はありません。それは、単に、仮説を立てていることですから。
しかし、その仮説を元に推論を重ねたときに、どうしても矛盾が出てしまう場合は、その仮説を棄却し、別の仮説を立てて推論してみるべきです。
そして、「(A)と(B)のクラスに互換性がある」という仮説を立てて推論すると、「ニューロンを解析し、科学的思考を積み重ねれば、いつかは「赤いという感覚それ自体」にたどり着くはずなのに、実際には、いくらニューロンを解析しても、「赤いという感覚それ自体」が見あたらない」という矛盾が生じますが、「(A)と(B)のクラスに互換性がない」という仮説を立てて推論すると、「ニューロンをいくら解析し、思考を積み重ねても、その思考は全て別クラスの思考なので、「赤いという感覚それ自体」には決してたどり着けないのは当たり前である。」ということになり、どこにも矛盾も謎も生じません。
ということは、ようするに、(A)と(B)のクラスには、互換性がないのです。
ここで、(B)とは何なのかをもっとよく考えてみると、これは、要するに、全ての科学的世界解釈の根幹です。現実世界を、物理化学的な体系として認識するということです。
別ないい方をすると、全ての科学的思考は、(B)の檻から外へは出られません。
全ての科学的思考のインスタンスは、(B)クラスとの互換性を持つことはできても、(A)クラスとの互換性は、決して持ち得ないのです。
結局南極、科学的思考によって脳内のニューロンに記述できるは「〜という物理現象」という思考でしかなく、科学的思考の積み重ねによって「〜という感覚」という直接的な感覚経験を脳内のニューロンに記述することは不可能なのです。
そして、全ての思考は脳内のニューロン塊の動的状態として記述されますから、脳内のニューロン塊の動的状態として記述できない直接的な感覚経験を扱うことは、不可能なのです。
ここが科学的思考の限界なのです。
直接的な感覚経験を記述する唯一の方法は、直接的な感覚経験それ自体でしかあり得ないのです。
ようは、「科学的・客観的・合理的思考を積み重ねれば、いつか科学的・客観的・合理的思考の限界の向こう側へ行ける」という勘違いが、意識の謎を生み出したのです。
このように考えると、たとえ世界の真の構造が②であったとしても、一番重要なところは全て辻褄が合い、本質的な謎はどこにも存在しなくなります。
赤いという感覚それ自体も、意識も、全ては、ニューロンの塊の動的状態に過ぎず、しかも、「赤いという感覚それ自体」は、科学的な記述は原理的に不可能なので、科学では記述できなくて当たり前だからです。
これで、意識の謎は解き終わりました。
なぜなら、世界の構造は、原理的に①か②のどちらかであり、①であっても②であっても、どちらも辻褄の合う説明が可能で、本質的な矛盾も謎も、もはや存在しないからです。
また、世界の真の構造が①と②のどちらであるかは、科学が無限に発達しようとも、原理的に解答不可能であるという結論が出ており、ここにも、矛盾も謎もありません。
なぜなら、科学が物理現象を対象とした体系であるために、
「意識が物理現象を超越したものであるかどうか」という問いには、原理的に答えることが不可能だからです。
そして、あとに残った意識の謎は全て各論です。
たとえば、ここでいう(A)と(B)のニューロン塊の動的状態は、本当にニューロン塊の動的状態なのか?脳全体に広がっている状態ではないのか?脳どころか、身体全体に広がっているのではないのか?いや、周囲の環境にまでも広がっているのではないのか(アフォーダンス理論)?単に脳の中だけだとしても、ダイナミックに部位を変えているのではないのか?具体的に脳のどの部位が、そのような活動をした結果、(A)や(B)になっているのか?(C)や(D)のような場所もたくさんあるのではないか?
しかし、それらは、ようは(A)や(B)の実装の詳細の話であって、(A)や(B)が単なるニューロン塊として実装されていようが、アフォーダンス理論で言うような環境も含めたものであろうが、それらは問題の本質とは関係のない、枝葉末節です。
なぜなら、次の図のように、「赤い花を見て発火したニューロン塊だけでなく、その赤い花とその比較対象を含めた環境全体」が、「赤いという感覚それ自体」を構成しているのだとしても、「(A)「感覚それ自体」とは別に(B)『「感覚それ自体」の認識』が存在する、という2重構造があり、その2重構造が、見かけ上、意識の謎を作り出したのだ」という本質は、なんら変わらないからです。
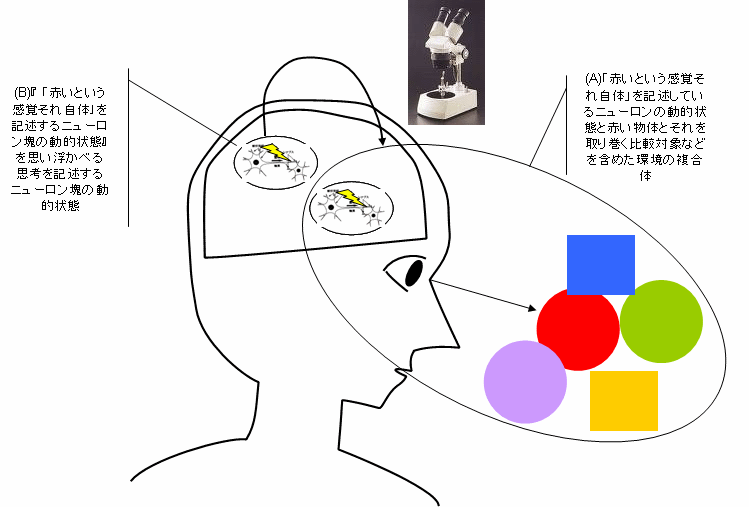
なので、これらは全て、賢く熱意のある科学者たちが地道に研究を積み重ねていけば少しずつ解けていく性質の謎、科学の枠内に収まる謎でしかありません。
で、よーするに、意識とはなんなのよ?
結局のところ、霊や魂などの超自然的なものを信じない人にとっては、
この、「現に世界が見えている感じ」というのは、よーするに、何なのでしょうか?
「何」が世界を見ているのでしょうか?
この世界を見ている、その主体は何なのでしょうか?
物理現象を超越したものを信じないのですから、答えは明らかです。
よーするに、「ある特定のニューロン塊が分子的・電気的にある活動をする」ということと、
「その特定のニューロン塊が世界を見る」ということは、完全に同一のことなのです。
つまり、ニューロン塊の分子的・電気的活動状態が、世界を「見て」いるのです。
「物理現象」が世界を「見て」いるのです。
「現に世界を見る」ことのできる物理現象と、そうでない物理現象の区別はあるのでしょうか?
ニューロン塊の動的状態が、「現に世界を見る」ことのできる物理現象なのは、
外界の情報を、対応する電気信号や分子活動に翻訳することができるからなのでしょうか?
もし、そうだとすれば、他の動物や虫どころか、コンピュータも「現に世界を見ている」ことになります。
もし、そういう制約がなく、単に、外界の変化に応じて、自分の物理状態を変化させれば、それで「現に世界を見ている感じ」が生じるのであれば、海や川や大気ですらも、「現に世界を見ている」ということになります。
もっというと、あらゆる物理現象は、存在することそれ自体で、「現に何かを見ている感じ」を持っているのかもしれません。
だとすると、この世界のあらゆる物理現象には、意識があることになります。
この宇宙に、真の真空はありません。
量子のレベルで見れば、真空は揺らいでいるのです。
ということは、真空も含めた、宇宙のあらゆる物理状態は、すべて意識があるのかも知れません。
しかし、この、「現に世界が見えている感じ」が、ある特定の物理現象にあるのかどうかは、原理的に分かりません。
単なる物理現象どころか、自分以外の人間が「現に世界が見えている感じ」を持っているのかどうかすら、原理的に確かめようがないのです。
この疑問は、「原理的に確かめようがない」ということで、完全に結論が出てしまっており、謎も矛盾もどこにもないのです。
*1:現在はまだ、観測機器の性能の問題から、細かい部分まで直接リアルタイムで見えるわけじゃないですが